『リーン開発の現場』の翻訳は@kakutaniの背中を見ながらの作業でした。それを言語化するのは難しいのですが、ポイントみたいなものはやはりあり、そういった気づきをFacebookのノートに書きためていたので、今日はそれを公開してみようと思います。
翻訳初期に気がついたこと
2013年3月頃にメモしていた内容です。英語のことと日本語のこと、その両方を考えるのが大変でした。
- 「本当に、実際」といった意味が重複している箇所はまとめたほうが読みやすい
- 原文の形だと意味がわかりにくい場所は、文章を並び替えると読みやすくなる場合がある。大きく変えたときは気がつくように印をいれておくとよい
- 過去と現在といった時勢を間違えていたり、時勢がコロコロかわったりしている場合があった。章や節など、大きな単位で見直していく必要がある
- 「Also」の「〜も」とか「〜もまた」みたいな意味がロストしているところがいくつかあった。そういった部分は、読みにくくても文に入れておき、あとで読みやすさ優先にするため、言葉を置き換えたり消したりした
- はじめのうち、文章の書き換えは気にしなくても良さそう。後半になると注意して変更が必要になる。
- 単語の置き換えは変える前に相談したほうがいい
- 原文から大きく変えざるをえない表現は「原文は〜」のように目印を入れておく
- 「and」は「AとB」や「AかつB」のように意味が変わる場合があるので注意
- 「〜を〜に」の順に文章を並べ替えると読みやすい
レビューで学んだこと
レビューではたくさんのフィードバックを頂きました。以下はその一部です。
- 「こと」をつい使ってしまうので気をつける 「わかることができる」 > 「わかる」、「利用することができる」>「利用できる」
- 異なる漢字をとなり同士にしない。「今止めているもの」 > 「今、止めているもの」
- 受身は能動態に変えた方が分かりやすい
- もとの意味が残っているときは漢字のまま、そうでないときは文字をひらく(ひらがなにする)
- ので、から、ために => それぞれ原因、理由、目的で使い分けを行う
文章の書き方本などで学んだこと
『「超」文章法 (中公新書)』、『理科系の作文技術 (中公新書)』は翻訳中に読みました。なかでも、『日本語スタイルガイド第2版』が一番自分には役に立ちました。
- 主語が複数ある文は分解するとわかりやすい。ただ、訳し過ぎに注意すること
- 「?」「!」のあとには全角スペースを入れる
- 「…」は「……」と2回書く
- 英文は、, ; : . の順で強い区切りになるらしい。:コロンは「すなわち」に置き換えることができるそうだ
- 接続詞で文の関係を説明するので意識する
- 代名詞は極力さける(アジャイルサムライを見てみよう!)
- 「、」は雰囲気でつけるものらしい。ルールがないので読みやすさ優先で
- 日本語は時勢が適当なので、意味と読みやすさベースで考えたほうがいい
- 「A,B,C and D」とか「A,B,C or D」という書き方は英語だと固定らしい(2択しかない)。こういうときは、「A、B、CとDが」とかくと論理和とかを考えちゃって「A, B, (C, D)」と考えてしまうので、「AとBとCとDが」か「AやB,C,Dが」と訳すのがシンプルになる
まとめ
今日公開したメモの内容は、翻訳だけでなく文章の書き方の参考にもなるかもしれません。
あらためてメモを見てみると、いろんなことを考えながら文章を読み、書いていることに気がつきます。技術書を編む作業は大変なのですが、なかなかやりがいのある仕事でした。
参考資料
- 『表記規則:企業サイトで使用する「ひらく漢字」「ひらかない漢字」』感じの開き方の参考にさせていただきました。最後の方はオーム社eStoreで販売されている『アジャイルサムライ』のPDFを使ってあわせるようにしています
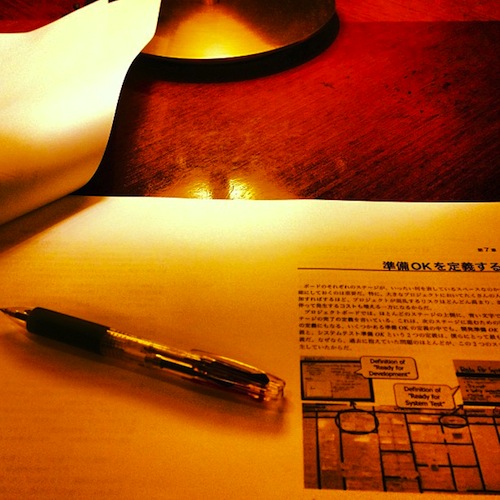

コメントを残す